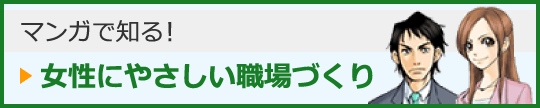���������̕�
�����Ȃ�����S���ĔD�P�E�o�Y���}���邽�߂�
�����}�}�̈玙�ɂ���
�玙�x��
�J���҂́A�\���o�邱�Ƃɂ��A�����Ƃ��Ďq��1�ɒB����܂ł̊ԁA�玙�x�Ƃ����邱�Ƃ��ł��܂��i���͈̗̔͂L���ٗp�J���҂��ΏۂƂȂ�܂��j�B
�玙�x�ƂƂ͕ʂɁA�q�ǂ��̏o����8�T�Ԉȓ���4�T�Ԃ܂ŁA�Y��p�p��x�i�o�����玙�x�Ɓj���擾���邱�Ƃ��ł��܂��B
���̏ꍇ�A�q��1��6��������2�ɒB����܂ł̊ԁA�玙�x�Ƃ����邱�Ƃ��ł��܂��B
�i�玙�E���x�Ɩ@��5���`��9����6�j
���Ώ�
�玙�x�Ƃ��ł���J���҂́A�����Ƃ���1�ɖ����Ȃ��q����{�炷��J���҂ł��B���X�ٗp�����҂͑ΏۂɂȂ�܂���B�J�g����̒����ɂ��A�玙�x�Ƃ��ł��Ȃ��ꍇ������܂��B
���͈̗̔͂L���ٗp�J���҂́A�玙�x�Ƃ��Ƃ�܂��B
�u�J�g����̒����ɂ��A�玙�x�Ƃ��ł��Ȃ��ꍇ�v�́A���̂����ꂩ�ł��B
- �E�ٗp���Ԃ�1�N�����̘J����
- �E�玙�x�Ɛ\�o�̓�����1�N�ȓ��Ɍٗp���Ԃ��I������J���ҁi1��6�����܂ŋy��2�܂ł̈玙�x�Ƃ̏ꍇ�́A6�����ȓ��ɏI������ꍇ�j
- �E1�T�Ԃ̏���J��������2���ȉ��̘J����
�u���͈̗̔͂L���ٗp�J���ҁv�Ƃ�
�u�玙�x�Ƃ̑ΏۂƂȂ���͈̗̔͂L���ٗp�J���ҁv�Ƃ́u�q��1��6�����ɂȂ���̑O���܂łɘJ���_��i�X�V�����ꍇ�ɂ́A�X�V��̌_��j�̊��Ԃ��������邱�Ƃ����炩�łȂ����Ɓv�ɊY������J���҂ł��B
- ���玙�x�Ɠ��̑ΏۂƂȂ�u�q�v�͈̔͂́A�@����̐e�q�W������q�i�{�q���܂ށj�̂ق��A���ʗ{�q���g�̂��߂̎����I�ȗ{����Ԃɂ���q�A�{�q���g���e�Ɉϑ�����Ă���q�A���Y�J���҂�{�q���g���e�Ƃ��Ĉϑ����邱�Ƃ��K���ƔF�߂��Ă���ɂ�������炸�A���e�������������Ƃɂ��A���Y�J���҂�{�痢�e�Ƃ��Ĉϑ����ꂽ�q�������܂��B
- ���Y��p�p��x�i�o�����玙�x�Ɓj
�q�ǂ��̏o����8�T�Ԉȓ���4�T�Ԃ܂ň玙�x�ƂƂ͕ʂɋx�Ƃł��鐧�x�ł��B
���Y��p�p��x���̏A�Ɓ�
�J�g�����������Ă���ꍇ�Ɍ���A�J���҂��ʂɍ��ӂ����͈͂ŁA�Y��p�p��x�̋x�ƒ��ɏA�Ƃ��邱�Ƃ��ł��܂��B
������
�����Ƃ��Ďq��1�ɒB����܂ł̊ԂŁA�J���҂��\���o�����Ԃł��B
�������A�z��҂��玙�x�Ƃ����Ă���Ȃǂ̏ꍇ�́A�q��1��2�����ɒB����܂ŏo�Y���A�Y��x�Ɗ��ԁA�玙�x�Ɗ��ԁA�Y��p�p��x���Ԃ����v����1�N�Ԉȓ��̋x�Ƃ��\�ł��i�p�p�E�}�}��x�v���X�j�B
����ȂƂ��͂ǂ���������́H
�ۈ珊�������œ����ł��Ȃ��āA�q�ǂ���1�̒a�����܂łɐE�ꕜ�A��������c�B�玙�x�Ƃ̉����͂ł���́H
���̏ꍇ�ɂ́A�q��1��6�����ɒB����܂ň玙�x�Ƃ��ł��܂��B�܂��A1��6�������B���_�ł��ۈ珊�ɓ����ł��Ȃ����̏ꍇ�́A�q��2�ɒB����܂ň玙�x�Ƃ��ł��܂��B
1��6�����i����2�j�܂ň玙�x�Ƃ��ł���̂́A����1�A2�̂����ꂩ�̎������ꍇ�ł��B
- 1.�ۈ珊���̓����\���݂��s���Ă��邪�A�����ł��Ȃ��ꍇ
- 2.�q�̗{����s���Ă���z��҂ł����āA1�i����1��6�����j�ȍ~�q��{�炷��\��ł������҂��A���S�A�����A���a���̎���ɂ��q��{�炷�邱�Ƃ�����ɂȂ����ꍇ
- ���玙�x�ƒ��̘J���҂��p�����ċx�Ƃ���ق��A�q��1�i����1��6�����j�܂ň玙�x�Ƃ����Ă����z��҂ɑւ���Ďq��1�̒a�����i����1��6�������B���̗����j����x�Ƃ��邱�Ƃ��ł��܂��B
�܂��A1��6�����i����2�j�܂ł̈玙�x�Ƃ��擾���Ă��Ȃ��ꍇ�A�z��҂̋x�Ƃ̏I���\����̗����ȑO�̓����A�{�l�̈玙�x�ƊJ�n�\����Ƃ��邱�Ƃ��ł��܂��B
����
���Y��p�p��x�̉�
2��܂ŕ����\�ł��B�i2�܂Ƃ߂Đ\���o����K�v����j
��1�܂ł̈玙�x�Ƃ̉�
�q1�l�ɂ��A�v�w�Ƃ���2��܂ŕ������Ď擾���\�ł��B
�i�p�p�E�}�}��x�v���X�̏ꍇ��1��2�����܂Łj
�ȉ��̂悤�ȓ��ʂȎ���������ꍇ�ɂ́A�ēx�̈玙�x�Ǝ擾���\�ł��B
���ʂȎ���Ƃ́A���̂����ꂩ�̏ꍇ�ł��B
- ①�V���ȎY�O�E�Y��x�ƁA�Y��p�p��x�A�玙�x�Ɩ��͉��x�Ƃ̊J�n�ɂ��玙�x�Ƃ��I�������ꍇ�œ��Y�x�ƂɌW��q���͉Ƒ������S�������ꍇ
- ②�z��҂����S�����ꍇ���͕����A���a�A��Q�ɂ��q�̗{�炪����ƂȂ����ꍇ
- ③�������ɂ��z��҂��q�Ɠ������Ȃ����ƂƂȂ����ꍇ
- ④�q�������A���a�A��Q�ɂ��2�T�Ԉȏ�ɂ킽�萢�b��K�v�Ƃ���ꍇ
- ⑤�ۈ珊����������]���Ă��邪�A�����ł��Ȃ��ꍇ
- ���q��1�Έȍ~�̋x�Ƃɂ��ẮA�q��1�܂ł̈玙�x�ƂƂ͕ʂ�1�擾�\
- ��1�Έȍ~�̋x�Ƃɂ��ď�L�@�̎���������ꍇ�Ɍ���A1��6��������2�܂ł̈玙�x�Ƃ��ēx�̎擾���\
���玙�x�Ɛ\�o
���\�o�̓��e��
�\�o�̔N�����A�J���҂̎����A�\�o�ɌW��q�̎����A���N�����A�J���҂Ƃ̑����A�x�ƊJ�n�\����y�ыx�ƏI���\���
���Y��p�p��x�̐\�o�̊�����
�x�ƊJ�n�\��������]�ʂ�x�Ƃ���ɂ́A��������2�T�ԑO�܂łɐ\���o�܂��B
��1�܂ł̈玙�x�Ƃ̐\�o�̊�����
�x�ƊJ�n�\��������]�ʂ�x�Ƃ���ɂ́A��������1�����O�܂łɐ\���o�܂��B
��1����1��6�����i����1��6��������2�j�܂ł̈玙�x�Ƃ̐\�o�̊�����
�x�ƊJ�n�\����i1�̒a�����j�����]�ʂ�x�Ƃ���ɂ́A����2�T�ԑO�܂łɐ\���o�܂��B
�q����ĂȂ��瓭�������邽�߂�
�玙�̂��߂̒Z���ԋΖ�
3�ɖ����Ȃ��q��{�炷��j���J���҂ɂ��āA���Ǝ�͒Z���ԋΖ����x�i1�������Ƃ���6���ԁj��݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂��B
�i�玙�E���x�Ɩ@��23���j
���Ώ�
3�ɖ����Ȃ��q��{�炷��j���J���҂ł��B1���̘J�����Ԃ�6���Ԉȉ��̎ҋy�ѓ��X�ٗp�����҂͑ΏۂɂȂ�܂���B�J�g����̒����ɂ��A�Z���ԋΖ����ł��Ȃ��ꍇ������܂��B
�u�J�g����ɂ��K�p���O�v�Ƃ��邱�Ƃ��ł���͎̂��̂����ꂩ�ł��B
- �E�ٗp���Ԃ�1�N�����̘J����
- �E�Ɩ��̐������͋Ɩ��̎��{�̐��ɏƂ炵�āA�Z���ԋΖ����x���u���邱�Ƃ�����ƔF�߂���Ɩ��ɏ]�����Ă���J����
- �E1�T�Ԃ̏���J��������2���ȉ��̘J����
- ���ΏۊO�ƂȂ�Ɩ��͈̔͂���̓I�ɒ�߂邱�Ƃ��K�v�ł��B
�J�g����ɂ��u�Ɩ��̐������͋Ɩ��̎��{�̐��ɏƂ炵�āA�Z���ԋΖ����x���u���邱�Ƃ�����ƔF�߂���Ɩ��ɏ]�����Ă���J���ҁv�Ƃ��ēK�p���O�Ƃ��ꂽ�J���҂Ɋւ��ẮA���̂����ꂩ�̑[�u���u����悤���Ǝ�ɋ`���t�����Ă��܂��B - �E�玙�x�ƂɊւ��鐧�x�ɏ�����[�u
- �E�n�Ǝ����̕ύX��
- �E�e�����[�N
- ���玙�Z���ԋΖ����x�͂��ꂼ��̉�ЂŋΖ����ԑѓ���̓I�ȓ��e����߂��Ă��܂��B �A�ƋK���Ȃǂʼn�Ђ̐��x���m�F���܂��傤�B
����O�J���̐����i�c�ƖƏ��j
���Ǝ�́A���w�Z�A�w�̎n���ɒB����܂ł̎q��{�炷��J���҂����������ꍇ�ɂ́A���Ƃ̐���ȉ^�c��W����ꍇ������ �A����J�����Ԃ��ĘJ�������Ă͂Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂��B
1��̐����ɂ��A1���ȏ�1�N�ȓ��̊��ԗ��p�ł��܂��B�J�n���y�яI�����𖾂炩�ɂ��Đ����J�n�\�����1�����O�܂łɐ�������K�v������܂��B���̐����́A��������邱�Ƃ��ł��܂��B
�i�玙�E���x�Ɩ@�@��16����8�j
���ԊO�J���̐���
���Ǝ�́A���w�Z�A�w�̎n���ɒB����܂ł̎q��{�炷��J���҂��q��{�炷�邽�߂ɐ��������ꍇ�ɂ́A���Ƃ̐���ȉ^�c��W����ꍇ�������A 1����24���ԁA1�N150���Ԃ��Ď��ԊO�J���������Ă͂Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂��B1��̐����ɂ�1���ȏ�1�N�ȓ��̊��ԗ��p�ł��܂��B�J�n���y�яI�����𖾂炩�ɂ��Đ����J�n�\�����1�����O�܂łɐ�������K�v������܂��B���̐����́A��������邱�Ƃ��ł��܂��B
�i�玙�E���x�Ɩ@�@��17���j
�[��Ƃ̐���
���w�Z�A�w�̎n���ɒB����܂ł̎q��{�炷��J���҂��q��{�炷�邽�߂ɐ��������ꍇ�ɂ́A���Ǝ�͌ߌ�10���`�ߑO5���i�u�[��v�j�ɂ����ĘJ�������Ă͂Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂��B1��̐����ɂ�1���ȏ�6�����ȓ��̊��ԗ��p�ł��܂��B�J�n���y�яI�����𖾂炩�ɂ��Đ����J�n�\�����1�����O�܂łɐ�������K�v������܂��B���̐����́A��������邱�Ƃ��ł��܂��B
�i�玙�E���x�Ɩ@�@��19���j
�q�̊Ō쓙�x��
���w�Z��R�w�N�C���܂ł̎q��{�炷��J���҂́A���Ǝ�ɐ\���o�邱�Ƃɂ��A�P�N�x�ɂ����ĂT���i�{�炷�鏬�w�Z��R�w�N�C���܂ł̎q���Q�l�ȏ�̏ꍇ��10���j�����x�Ƃ��āA�P���P�ʖ��͎��ԒP�ʂŎq�̊Ō쓙�x�ɂ��擾���邱�Ƃ��ł��܂��B�a�C�E�����������q�̐��b�A�\�h�ڎ�⌒�N�f�f���A�q�̎��a�̗\�h��}�邽�߂ɕK�v�Ȑ��b�A�����ǂɔ����w�������ɔ����q�̐��b�A�q�̓����i���w�j���A�������ւ̎Q���̂��߂Ɏ擾���邱�Ƃ��\�ł��B
�i�玙�E���x�Ɩ@�@��16����2�A��16����3�j
�_��ȓ��������������邽�߂̑[�u�i���ߘa7�N10������j
3���珬�w�Z�A�w�O�̎q��{�炷��J���҂ɂ��āA���Ǝ�́A�u�n�Ǝ������̕ύX�v�A�u�e�����[�N��(10��/��)�v�A�u�ۈ�{�݂̐ݒu�^�c���v�A�u�A�Ƃ��q��{�炷�邱�Ƃ�e�Ղɂ��邽�߂̋x�Ɂi�{�痼���x���x�Ɂj�̕t�^(10��/�N)�v�A�u�Z���ԋΖ����x�v�̒�����A2�ȏ�̑[�u��I�����ču���Ȃ���Ȃ�܂���B�J���҂͉�Ђ��u�����[�u�̒�����1��I�����ė��p���邱�Ƃ��ł��܂��B
�i�玙�E���x�Ɩ@ ��23����3�j
���������������x
- �����E���������̉����y�ђ���
- �J�g�Ƃ��玙�x�Ƃ̎擾���ɔ����J�g�Ԃ̕����ɂ��āA�s���{���J���ǒ��ɂ�镴�������̉����y�ђ���ψ��ɂ�钲��x�𗘗p���邱�Ƃ��ł��܂��B
���̐��x�E�[�u�Ɋւ��ĕ��������������s�Ȃ��܂��B
- 1.�玙�x�Ɛ��x
- 2.�Y��p�p��x�i�o�����玙�x�Ɓj���x
- 3.���x�Ɛ��x
- 4.�q�̊Ō쓙�x�ɐ��x
- 5.���x�ɐ��x
- 6.����O�J���̐���
- 7.���ԊO�J���̐���
- 8.�[��Ƃ̐���
- 9.�玙�̂��߂̏���J�����Ԃ̒Z�k�[�u
- 10.���̂��߂̒Z���ԋΖ����x���̑[�u
- 11.�{�l���͔z��҂̔D�P�E�o�Y���̐\�o���������ꍇ�̑[�u
- 12.�{�l���͔z��҂̔D�P�E�o�Y���̐\�o�𗝗R�Ƃ���s���v�戵��
- 13.�Y��p�p��x���̏A�Ɖ\������\�o�E���ӂ��Ȃ��������Ɠ��𗝗R�Ƃ���s���v�戵��
- 14.�玙�x�Ɓi�Y��p�p��x���܂ށj�E���x�Ɠ��𗝗R�Ƃ���s���v�戵��
- 15.�玙�x�ƁE���x�Ɠ��Ɋւ���n���X�����g�̖h�~�[�u
- 16.�玙�x�ƁE���x�Ɠ��Ɋւ���n���X�����g�̑��k���s�������Ɠ��𗝗R�Ƃ���s���v�戵��
- 17.�J���҂̔z�u�Ɋւ���z���[�u
- 18.�ΏۉƑ��̉���K�v�Ƃ���Ɏ��������Ƃ̐\�o���������ꍇ�̑[�u
- 19.�ΏۉƑ��̉���K�v�Ƃ���Ɏ��������Ƃ̐\�o�𗝗R�Ƃ���s���v�戵��
- 20.���ɒ��ʂ���O�̑����i�K�i40�Γ��j�ł̏����̑[�u
- 21.�D�P�E�o�Y���̐\�o����q���R�ɂȂ�O�̎����Ɋm�F���ꂽ�J���҂̎d���ƈ玙�̗����Ɋւ���ӌ��̓��e�𗝗R�Ƃ���s���v�戵��
- 22.3���珬�w�Z�A�w�̎n���ɒB����܂ł̎q��{�炷��J���҂̏_��ȓ��������������邽�߂̑[�u
- 23.3�ɂȂ�܂ł̓K�Ȏ����̌ʂ̎��m�E�ӌ��m�F�̑[�u
�ڂ����͌����J���ȃz�[���y�[�W�u�E��ł̃g���u�������̉��������߂���ցv���������������B
�܂��A���x�Ɛ��x�ɂ��ẮA�u�玙�E���x�Ɩ@�ɂ��āv���������������B
�֘A���
- �_��Ј��ł��Y�O�E�Y��x�Ƃ�玙�x�Ƃ͎��܂����H
- �玙�x�ƌ�A���A���ł��Ȃ��Ɖ�ЂɌ����܂����B
- �E�ꕜ�A��Ɍ��������z����܂������A�[���ł��܂���B
- �玙�x�Ƃ̌J��グ�I���͂ł��܂����B
- �玙�x�Ƃ͍Œ����N�܂Ŏ擾�ł��܂����H
- �Վ��E���A�����E���A�p�[�g�^�C�}�[�A�_��Ј��͈玙�x�Ƃ𐿋��ł���̂ł��傤���H
- �玙�x�ƒ��̋��^�͂ǂ��Ȃ�̂ł��傤���H
- �玙�x�ƕ��A��������E��ɖ߂肽���B�ǂ������炢���ł��傤���H
- �玙�̂��߂̋Ζ����ԒZ�k���̑[�u�Ƃ͂ǂ��������̂ł����H
- �玙�̂��߂̒Z���ԋΖ����x�𗘗p�����ꍇ�A���̊Ԃ̋����͂ǂ��Ȃ�̂ł��傤���H
- �}�Ȕ��M�Ȃǎq�ǂ��̕a�C���Ɏd�����x�߂Ȃ��Ƃ��A�}�Ȏc�Ƃŕۈ牀�̂��}���ɊԂɍ���Ȃ��Ƃ��ɑΉ����Ă��炦�鐧�x�ɂ͂ǂ�Ȃ��̂�����̂ł��傤���H
- �q�ǂ��̊Ō�x�ɐ��x�͒N�ł��K�v�Ȏ��ɗ��p�ł���ł��傤���B�q�ǂ��̔N����◘�p�ł�������������Ă��������B
- �q�ǂ��̑̒��������Ȃ�̂����O�ɕ�����͔̂��ɍ���ł��B�q�ǂ��̊Ō�x�ɂ��擾���邽�߂ɂ́A���O�ɐ\�����Ȃ��Ă͂����Ȃ��̂ł��傤���H
- �Ō�x�ɂ͖����ł��傤���H