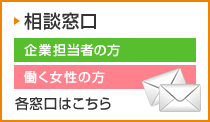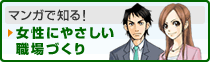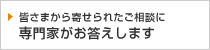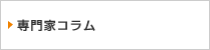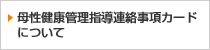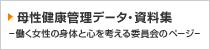|
働く女性の心とからだの応援サイト > 妊娠出産・母性健康管理サポート > 職場における母性健康管理の推進 > 女性労働者の役割 |
|
|
企業内で母性健康管理が有効に実施されるためには、母性健康管理にかかわる各関係者の役割を明確にし、連携のとれたひとつのシステムとして確立する必要があります。 |
|
「母子保健法」第4条において「母性は、みずからすすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。」と規定されています。法令で定められている保健指導又は健康診査は必ず受診しましょう。
|
健康診査の結果、症状等に関して指導を受けた場合には、医師等に職務内容や職場の状況について説明し、指導内容を「母健連絡カード」等に記入してもらい、事業主に提出します。医師等の指導事項が守れるように、勤務時間の変更、職務の軽減等必要な措置を申請します。
医師等から特に指導がない場合でも、通勤状況や健康状態によって、必要があれば、通勤緩和の措置や休憩時間の変更等の申し出をしましょう。
|
働きながら妊娠・出産することについて、特に初産婦であれば経験がないのでちょっとしたことでも大丈夫かなと思うことがあります。健康面での不安や仕事の問題等について躊躇することなく健康管理部門に相談したり、妊娠・出産を経験している先輩や同僚に相談してみましょう。 |
出産予定日が判明したら早めに届出をします。育児休業取得予定であれば、その旨も申し出ておきましょう。休業中の業務の引継ぎ等を確実に行うことはもちろんのこと、上司、同僚との連絡を密にする等理解を得るよう努めましょう。
産褥期の終わる6〜8週までは注意を要するので、必要があれば健康診査等を受診するための時間を請求します。また、医師等の指導を受けた場合は、その内容を「母健連絡カード」等により事業主に伝達し、必要な措置を申請しましょう。
母性健康管理とは
ご相談窓口
ダウンロード
企業ご担当者の方
一般財団法人 女性労働協会
〒105-0014 東京都港区芝2-27-8 VORT芝公園8階厚生労働省委託 母性健康管理サイト
(C) Ministry of Health, Labour and Welfare, All Rights Reserved.