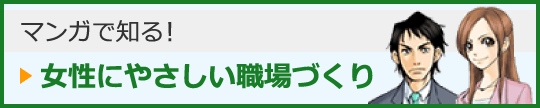企業ご担当者の方

母性健康管理制度について人事管理部門、上司それぞれの役割りをご紹介します。
制度・設備の整備、周知
人事管理部門では、健康管理部門等の意見を聞いて母性健康管理に関する社内体制を整備する必要があります。また、これらの社内制度についての周知、教育の実施を健康管理部門との連携を図りながら進めていくことが求められます。
業務の点検
妊産婦に対する就業制限のある業務を明確にしておきます。また、健康管理部門の意見を聞きながら、妊産婦にとって負担の大きい業務のリストアップをしておきます。
相談窓口の明確化・時間等の配慮
母性健康管理の相談窓口を明確にして、気軽に相談できる体制にしておいてください。健康管理部門に直接相談したい旨の申し出があった場合は、時間等の配慮をします。
妊娠の申し出の受理
妊娠の申し出は女性労働者の意思を尊重しますが、女性労働者が妊娠したことを言い出しやすい職場環境を日頃からつくっておくことが望まれます。
POINT!
妊娠の申し出先や妊娠の申し出方法を明確にし、日頃から女性労働者へ周知することが望ましいでしょう。
| 申し出方法 ⇒口頭による申し出 ⇒所定書類による申し出 ⇒他に必要なものは? |
申し出先 ⇒上司 ⇒人事 ⇒総務 ⇒健康管理者 |
通院休暇申請の受理
妊娠の申し出のあった女性労働者に対し、職場の上司はできる限り、医師等が指定した日に健康診査を受診できるよう配慮してください。人事管理部門は通院時間の確保や人員のやりくり等、女性労働者本人が通院できる環境整備を整えてください。
POINT!
通院休暇制度を設けることが望ましいですが、女性労働者本人が受診のため年次有給休暇を利用する場合には、半日単位での取得も可能とする等の配慮も望まれます。
未使用の有給休暇を積み立て妊娠時の通院や妊娠中の症状等への対応のための休暇等に利用できるようにしている企業の例もあります。
指導事項に基づく対応
妊娠中何らかの症状等があり、医師等によって就業上の配慮が必要と診断され「母健連絡カード」等の提出があった場合
指導事項に応じた措置を講じなければなりません。健康管理部門の意見を聞きながら必要な措置を考えることが重要です。とりわけ作業の軽減等具体的な措置の内容や、程度については必要に応じ、健康管理部門や医師等と協議して対応しましょう。なお、プライバシーの保護については十分配慮しましょう。
女性労働者本人または、健康管理部門からの報告により、就業上の配慮を行う必要がある場合
女性労働者本人と協議の上、例えば製造ラインの立ち作業から座作業に配置転換し負担を軽くする等、具体的な就業配慮を実行します。医師等の指導がなく、女性労働者から通勤緩和の措置や休憩に関する措置の申し出がなされた場合は、健康管理部門や医師等と協議し適切な措置をとってください。
POINT!
妊娠に限らず就業配慮による離席等に対応するため、工場部門において、いざというときサポートするリリーフマン制度を持っている企業の例もあります。日頃から環境を整えておくことが望まれます。
産前・産後休業届出の受理
休業中の対応や復職後の仕事について女性労働者本人と十分話し合いましょう。
POINT!
女性労働者の休業に伴う不安を取り除くために(例)
<A社>
産休前及び復職後の2回、女性労働者本人、上司、人事部門の三者で面接を行い、業務引継ぎ、復職後の仕事について話し合って、休業中の業務面での対応を検討
<B社>
復職にあたって健康管理部門と連携を取り、保健師が勤務上の悩み等の相談を受付
<C社>
代替要員を確保するために、退職者を登録している子会社から代替要員を派遣してもらい休業者への対応を行う
産後・復職後の対応
女性労働者から産後の回復不全等の症状で健康診査等を受診するための通院休暇が申請された場合は通院時間を確保します。また、「母健連絡カード」等が提出された場合は、上記(指導事項に基づく対応)のとおり実施します。産褥期(産後6〜8週)の女性労働者が職場復帰することについて、健康管理部門と連携をとりながら、健康管理への配慮を行ってください。
育児時間申請の受理
1歳未満の子を育てる女性労働者から請求があれば1日2回各々少なくとも30分の育児時間を与える必要があります。