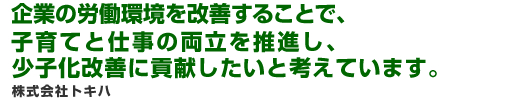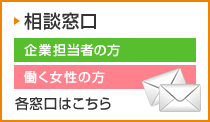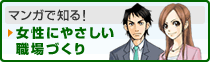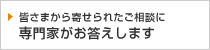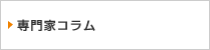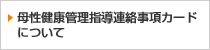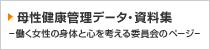働く女性の心とからだの応援サイト > 妊娠出産・母性健康管理サポート > 職場における母性健康管理の推進 > 社内体制の参考事例 > 株式会社トキハ |
|
職場における母性健康管理の推進に当たって、社内体制の参考になる好事例をご紹介します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 妊娠初期 | 妊娠中 | 産前・産後 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健診時間 の確保 |
通勤緩和 | 休憩時間 の確保 |
施設整備 | 時間短縮 勤務 |
業務転換、 就業制限 |
相談窓口 の設置 |
産前・ 産後休業 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 育児中 | 全期 | ||||||
| 育児時間 | 育児休暇・休業 | 経済的 支援 |
職場復帰支援 | 情報提供 | 研修の 実施 |
風土 づくり |
検討体制 づくり |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
健診時間の確保 |
本人の申し出により、通院に必要な時間についての遅刻、早退、外出を認めています。シフト勤務制なので、健診日を避けてシフトを組むなどして対応している者が多いのが現状です。 もちろん届け出が提出されれば、通院のために必要な時間についての遅刻・早退・外出は認めています。 〈母健カードの活用法〉 〈有給/無給〉 |
通勤緩和 |
医師等より通勤緩和の指導を受けた旨の申し出があった場合は、時差通勤を認めています。 〈有給/無給〉 |
休憩時間の確保 |
|
本人の申し出により所定の休憩時間以外に、適宜休憩することを認めています。 〈有給/無給〉 |
施設設備 |
|
医務室(ベッド6台)及び、休憩室を設置しています。 |
時間短縮勤務 |
本人の申し出があった場合は、勤務時間の短縮を認めています。 〈勤怠管理の方法〉 〈有給/無給〉 |
業務転換、就業制限 |
〈転換先の決定方法〉 |
相談窓口の設置 |
医務室には健康相談室を設置しているので、母性健康管理に限らず健康に関する相談を受け付けています。妊娠した女性労働者は、体調に関する相談は医務室に、制度に関する相談は人事部に持ちかけるケースが多いようです。 |
産前・産後休業 |
|
〈取得できる期間〉 〈代替要員の確保〉 引き継ぎに関しては、産休取得者の仕事を、代替要員にいきなり引き継ぐのではなく、まずは、いつも同じ職場で働いている職員が仕事を引き継ぎ、代替要員は、その補佐をする形で少しずつ仕事を覚えてもらいます。日ごろ一緒に仕事をしている職員なので、産休取得者の仕事内容もある程度把握しており、引き継ぎもスムーズにできます。 〈有給/無給〉 |
育児時間の確保 |
30分の休憩を1日2回まで取得できます。 〈有給/無給〉 |
──勤務時間の短縮について、具体的な取り組みをお聞かせください。 |
育児短時間勤務を導入しています。子どもが小学校1年生の2学期開始前まで利用することができ、 出勤及び退勤時間を、1時間単位で最大4時間まで短縮することが可能です。 〈勤怠管理の方法〉 〈有給/無給〉 |
育児休暇、育児休業 |
〈育児休業の期間〉 〈有給/無給〉 〈代替要員の確保〉 〈業務の引き継ぎ〉 |
経済的支援 特にありません。 |
職場復帰支援 |
育児休業の取得者がスムーズに職場復帰できるよう、社内報を定期的に発送しています。 職場復帰については、育休取得前に決定しておきますが、保育園との調整もあるので、一度だけ変更することができます。復帰にあたっては、出産経験のある人事担当者が相談に乗っているので、復帰支援制度の説明だけでなく、保育所の問題や育児に関するアドバイスまでできるようになっています。 |
制度に関する情報提供 |
|
〈情報提供のツール〉 〈情報を提供するタイミング〉 |
研修の実施 〈研修対象者〉 〈実施のタイミング〉 |
風土・社内環境づくり
現在、産休・育休の取得率も100%となり、「取得するのが当たり前」という状況になっていますが、制度導入当初は「忙しい時期に休まれては困る」というような反応を示す社員がいないわけではなかったのです。 |
検討体制づくり 2ヶ月に1回程度、各売り場を巡り実態調査を行うようにしています。昨年は、短時間勤務制度を活用している労働者のいる売り場に出向き、「決められた時間に帰宅できているか」、「困ったことはないか」など、ヒアリングを行います。 今後も、こうした調査を続けていきながら、上がってきた意見を元に、運用方法の変更や規定の見直し等を行っていきたいと考えています。 |
実施体制・各部門の役割
妊娠の報告は、人事に直接上がるわけではなく、まず、直属の上司に報告します。そのため、人事では妊娠初期の段階で把握することができません。「人事への報告を義務づけるべきでは…」という議論が出たこともあったが、知られたくない人もいるだろうし、強制するのは良くないということになり義務づけませんでした。 |
| 前のページ | | | 次のページ |
母性健康管理とは
ご相談窓口
ダウンロード
企業ご担当者の方
一般財団法人 女性労働協会
〒105-0014 東京都港区芝2-27-8 VORT芝公園8階厚生労働省委託 母性健康管理サイト
(C) Ministry of Health, Labour and Welfare, All Rights Reserved.