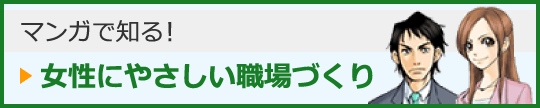妊娠・出産等、育児・介護休業等を
理由とする不利益取扱いの禁止と妊娠・出産等、
育児・介護休業等に関するハラスメントの防止
男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法では、事業主が「妊娠・出産」「育児休業等の申出や取得等」を理由とする解雇等の不利益取扱いをすることを禁止しています。
平成29年1月からは、妊娠・出産等、育児・介護休業等に関する上司・同僚による就業環境を害する行為を、従来から禁止されていた事業主が行う「不利益取扱い」と区別し、「職場における妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント」と整理し、事業主に対して防止対策を講じることを義務づけています。
このページでは、不利益取扱いとハラスメントについてご紹介します。
妊娠・出産等、育児・介護休業等を理由とする不利益取扱い
労働者が妊娠・出産したこと、産前・産後休業を取得したこと、妊娠中の時差出勤などの母性健康管理措置や深夜業免除などの母性保護措置を受けたことや、育児や介護のための制度を利用したこと等を理由として、解雇、減給、降格等の不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。


妊娠・出産等、育児・介護休業等を理由とするハラスメント
労働者が妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したこと等に関して、上司・同僚などによるハラスメントが問題になっています。
妊娠・出産等に関するハラスメントとは、上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した労働者の就業環境が害されることをいいます。
事業主は、職場における妊娠・出産等に関するハラスメントを防止する措置を講じることが義務づけられています。
なお、業務分担や安全配慮の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものはハラスメントに該当しません。


ハラスメントを防止するために事業主が講ずべき措置
職場における妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置が定められています。事業主は、これらを必ず実施しなければなりません。
〈事業主が講ずべき措置〉
・事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
・原因や背景となる要因を解消するための措置
・当事者等のプライバシーの保護のための措置の実施と周知
・相談・協力等を理由に不利益な取扱いを行ってはならない旨の定めと周知・啓発
社内に相談窓口がない時、会社が対応してくれない時は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ相談しましょう。
事業主からのハラスメント防止措置に関する相談等も受け付けています。
コラム
フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和6年11月1日から施行されました。
この法律はフリーランスが安心して働ける環境を整備するため、フリーランスと企業などの発注事業者との間の取引の適正化と、フリーランスの就業環境の整備を目的とした法律です。
就業環境の整備について、働く女性の母性健康管理に関連して、発注事業者がフリーランスに業務委託する際に留意すべき点は以下の2つです。
- 1. 6か月以上の業務委託について、フリーランスからの申出に応じて、妊娠、出産、育児または介護と業務を両立できるよう、必要な配慮を行わなければなりません。(同法第13条)
- 2. ハラスメント(いわゆるマタハラ等)によりフリーランスの就業環境を害することのないよう、適切に対応するために相談体制の整備など必要な措置を講じなければなりません。また、フリーランスがハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由として不利益な取扱いをしてはなりません。(同法第14条)
フリーランス・事業者間取引適正化等法の詳しい内容については、厚生労働省ホームページの「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」をご覧ください。