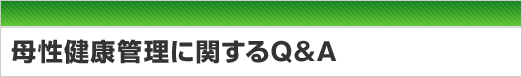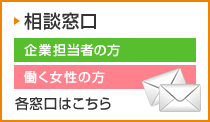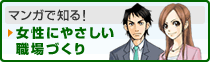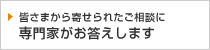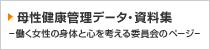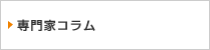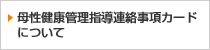働く女性の心とからだの応援サイト > 妊娠出産・母性健康管理サポート > 母性健康管理に関するQ&A |
|
|
| 妊産婦健診は本人の体調がよい場合でも行かせなければいけないでしょうか? |
| 事業主は、その雇用する女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならないとされています(男女雇用機会均等法第12条)。 妊産婦健診は母体や胎児の健康のため、妊産婦の体調に関わらず定期的に受診する必要がありますので、必ず受診できるよう時間の確保をしましょう。 |
| 保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間の確保とは具体的にどのような事をしなければいけないのでしょうか? |
| 女性は、妊娠すると、母体や胎児の健康のため、妊産婦のための保健指導又は健康診査を受ける必要がありますが、働く女性の場合は受診時間を確保することが困難な場合があることから、健診に必要な時間の確保が事業主に義務づけられています。 具体的には、女性労働者からの申出があった場合に、勤務時間の中で必要な時間を確保し、職場を離れて健康診査を受診できるようにする必要があります。 |
| 妊産婦健診以外に「妊婦教室」「母親学級」等があるようですが、「妊産婦健診」と同じ扱いをするのでしょうか? |
| 男女雇用機会均等法では、妊産婦本人を対象に行われる産科に関する診察や諸検査と、その結果に基づいて行われる個人を対象とした保健指導を、時間確保の対象としていますので、母親学級等集団指導は含まれません。ただし、このようなイベントに参加することで、妊娠・出産に対する不安を和らげることにもなりますので、参加できるように配慮することが望ましいでしょう。 |
| 妊娠中又は出産後の女性が妊産婦健診で休んだり、勤務時間短縮の制度を利用したことなどを勤務評価に反映させることは違法でしょうか? |
| 男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置(健康診査や保健指導を受けるための休暇の付与や勤務時間の短縮など)や労働基準法に基づく母性保護措置(産前・産後休業や深夜業の免除など)を受けたことなどを理由として、解雇などの不利益取扱いを行うことは、男女雇用機会均等法で禁止されています。これらを受けた労働者の勤務評価を行うに当たり不就労期間や労働能率の低下を考慮の対象とする場合において、私傷病で同じ期間休業した労働者と比較して不利に取扱うことは違反です。 |
◆症状等に対応する措置
| 妊娠中、通勤手段を一時的に変更(電車から自家用車)したときに事故にあった場合、労災等の対応は可能でしょうか? |
| 労災保険法で給付対象となる通勤とは「労働者が就業に関し住居と就業の場所との間の往復等を、合理的な経路及び方法により行うこと」と定めています。したがって、妊娠中の症状緩和のために通勤手段を変更した場合でも、労働者が一般的にとりうるものと認められれば、労災の対象となると考えられます。 また、企業が把握しておくために、社内規程に通勤届変更等の手続きを行うよう規定しておくことも有効であるといえます。 |
| 勤務時間の短縮や、休憩、休業の措置について、勤務しなかった時間分を給料から差し引いてもいいでしょうか。また、ボーナスの査定等に反映させることは違法でしょうか? |
| 勤務時間の短縮や休憩・休業によって実際に勤務しなかった時間分の賃金については、労使で話し合って決めることが望まれます。なお、平成16年度の厚生労働省の調査によると、通院休暇制度のある企業のうち、通院休暇が有給である企業の割合は46.7%となっています。 男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置(健康診査や保健指導を受けるための休暇の付与や勤務時間の短縮など)や労働基準法に基づく母性保護措置(産前・産後休業や深夜業の免除など)を受けたことなどを理由として、解雇などの不利益取扱いを行うことは、男女雇用機会均等法で禁止されています。これらを受けた労働者のボーナスの査定等を行うに当たり不就労期間や労働能率の低下を考慮の対象とする場合において、私傷病で同じ期間休業した労働者と比較して不利に取扱うことは違反です。 |
母性健康管理とは
ご相談窓口
ダウンロード
企業ご担当者の方
一般財団法人 女性労働協会
〒105-0014 東京都港区芝2-27-8 VORT芝公園8階厚生労働省委託 母性健康管理サイト
(C) Ministry of Health, Labour and Welfare, All Rights Reserved.