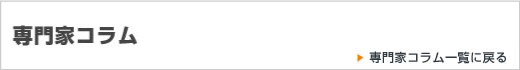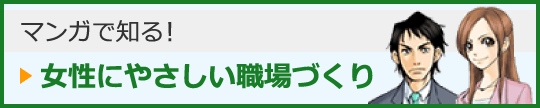SAC社会保険労務士法人 代表社員
吉山 敦子
妊娠・出産に関する社会保険

社会保険関係の諸手続きは自動的に行政がやってくれるのではなく、申請しないといけないものが多いことをご存知ですか?
出産や育児に関する法律は年々充実してきていますが、知らないと、せっかくの権利も無駄になりますので、平成25年8月1日現在の法律で、手続きなどの名称や概略を時系列的に書き出してみます。
1、入社したら…
先ず、就業規則などの会社の規程を確認しましょう。
就業規則は会社の法律です。妊娠・出産に関わらず、そう、男性労働者だってもちろん内容を確認しておく必要があります。
2、妊娠したら…
母体保護のために有害業務の制限や軽易業務への転換、時差通勤などが必要になるでしょう。会社への連絡手段として「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用するとスムーズです。また、切迫流産などで医師から労務不能とされ、休業して給与が不支給なら、健康保険から「傷病手当金」が支給される可能性があります。
3、妊娠7〜8ヵ月目になったら…
会社の担当者から説明を聞き、そろそろ必要な用紙等を確認しておきましょう。
4、出産予定日の6週間前…
産前6週間(多胎は14週間)、産後8週間はいわゆる「産休」期間です。産前は労働者の希望があれば、産後は希望の有無にかかわらず休業する期間(産後6週間経過後は、医師の認めた業務は就労可能)です。この間に休業して給与が不支給なら、健康保険から「出産手当金」が支給されます。分割して請求も可能ですが、産後休業終了後にまとめて1回で請求することが多いようです。
5、出産1ヵ月前…
以前は出産費用を病院へ支払っておき、後日「出産育児一時金」を健康保険から受け取りましたが、最近は健康保険から直接病院へ支払う「直接支払制度」を導入している病院が増え、労働者が全額を立替払いする必要がなくなりました。病院が制度を導入しているかどうか調べておきましょう。
6、出産前…
出産は病気ではないので健康保険対象外ですが、もし帝王切開になったら保険が適用されます。手術費が高額になるなら「限度額適用認定証」の交付を受けておきましょう。
7、出産したら…
会社へ報告しましょう。特に子供を自分の健康保険の被扶養者にする場合は、早めに会社へ連絡しておきましょう。
8、産休終了後…
育児休業をとるなら「育児休業等取得者申出書(社会保険料免除)」や雇用保険の「育児休業給付」の手続きがあり、会社が行ってくれますが、母子手帳のコピーなどが必要です。
9、職場復帰…
上記8の免除や給付は終了です。
10、復帰してから…
もし、短時間勤務などで給与額が減ったときは、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を会社が提出します。この場合、「養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出しておけば、将来の年金計算時には出産前の高い報酬額で計算してもらえます。
働きながらの出産や育児には会社や同僚の理解と協力が欠かせません。周囲への配慮を忘れずに、明るい職場環境を心掛けましょう。
関連情報
女性労働者が身体への負担を与えることのないよう配慮し、十分に能力を発揮することができる環境を整えてあげましょう。
働く女性の妊娠・出産・育児について法律で定められていることをご紹介します。
出産・育児に関する給付金等をご紹介します。
「母性健康管理指導事項連絡カード」は、医師等の女性労働者への指示事項が適切に事業主に伝達されるためのツールです。
妊娠中の症状や職場での対応、母性健康管理の取り組み、法律など、迷ったとき・困ったときの問合せ先です。