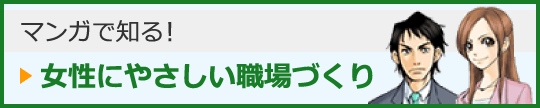賃金、賞与の支払い
産休等取得により出勤率を満たさない者への賞与の不支給
【事件名】Y法人事件
東京地裁:1998.3.25
東京高裁:2001.4.17
最高裁:2003.12.4
差戻し後東京高裁:2006.4.19
事件の概要
各種学校等を設置・運営する学校法人であるY法人(被告)に事務職として雇用された女性職員X(原告)が、就業規則に従って、産前6週間・産後8週間の休業をし、その後子が1歳に達するまで、朝夕合計1時間の育児短時間勤務制度を利用していたところ、賞与額の決定において、これらの期間・時間が欠勤扱いとされたため、賞与が一切支給されなかった。そこでXは、この扱いを不当として、賞与及び慰謝料を請求した。
Y法人では、賞与の支給要件として、対象期間の出勤率が90%以上という要件(90%条項)が定められていたことから、Xの出勤率が90%に満たないとして賞与の支給対象外となったものである。
決定要旨
第1審では、産前産後休業期間中及びその後30日間は解雇を禁止されていること、男女雇用機会均等法は妊娠・出産、産前産後休業の取得を理由とする解雇を禁止していること、年次有給休暇の取得要件の出勤率の算定において産休は出勤とみなすこととされていることなどをあげ、産休を労働者の責による不就労と区別して不利益を被らないようにしていると、その意義について述べ、産休を取得した女性を本人の責による不就労と同じ不利益を被らせることは、公序良俗に反し無効であるとしている(育児短時間勤務も同様)。
その上で、本件90%条項の趣旨は、従業員の貢献度を評価し、高い出勤率を確保することであって、一応の合理性があることを認めたが、それは欠勤、遅刻、早退などによる出勤率の低下を防ぐことにあり、産休や育児時間をこれらと同視することはできず、本件90%条項の適用により法が保護する権利を損なう場合は、これを損なう限度で同条項の合理性は認められないとしている。
Xは、平成6年度末賞与の対象期間中に8週間の産休を取り、平成7年度夏季賞与の対象期間中に育児時間を取ったため、いずれも90%条項により賞与が全く支給されなかったところ、この扱いはノーワークノーペイの原則により甘受すべき限度を超えており、このような措置が許されれば、労働者は不利益扱いを恐れて権利の行使を控え、更には出産を断念する事態が生じることが考えられる。そして、90%条項中、出勤すべき日数に産休の日数を算入し、出勤日数から産休の日数及び勤務時間短縮分を除外する部分は公序良俗違反としている。ただ、判決では、90%条項自体を無効としているわけではなく、無効の部分を除外した賞与の支給に関する条項を有効と認め、Y法人に対し一定の範囲で賞与の支払いを命じた。これについては、Y法人が控訴し、Xも附帯控訴したが、いずれも棄却された。
上告審では、法は産休や育児時間の取得を出勤扱いすべきことまで義務付けているわけではないから、その間を出勤扱いとするか否かは原則として労使に委ねられているとの基本的見解を示したが、原審において除外条項が公序に反する理由について具体的に示さないまま賞与の支払いを肯定した部分については法令違反があるとして、原審に差し戻した。
差戻後の控訴審においては、本件90%条項のうち、出勤すべき日数に産休の日数を算入し、出勤した日数に産休の日数及び勤務時間短縮分を含めないとしている部分は無効であるが、90%条項の一部が無効としても、産休日数及び勤務期間短縮分は欠勤として減額の対象となるとの判断を示した。産休期間や勤務時間短縮期間は、法律上賃金請求権はなく、就業規則上も無給とされているから、賞与の支給に関してこの不就労期間を欠勤扱いとしても不合理とはいえないこと、賞与額の減収がそれほど大きくないことを考え合わせると、除外条項を設けた就業規則の変更は合理的と認められるが、本件の場合、Y法人内で、除外条項により賞与の減額がされることが周知されなかった信義則違反があり、賞与の減額は許されない。
解説
本件は、4つの判決において、90%条項と賞与の不支給の可否について、かなり詳細に記述されていますが、要は、産前産後休業や勤務時間短縮分を、賞与の算定に当たって、自らの責任による不就労と同視して90%条項を適用することは、法律で認められた権利を抑圧するから許されないとする一方、これらの期間は就業規則上無給とされているから、出勤と同じ扱いをすることまで認められているものではなく、産休や勤務短縮時間に見合った賞与の減額は許されるとしたものです。
本件は、元々、Y法人においては、生理休暇、結婚休暇、忌引き休暇、配偶者出産休暇、産前産後休業が特別休暇として定められ、このうち産休だけが無給とされ、90%条項も存在していましたが、その具体的な運用については、その都度「回覧文書」によって職員に周知されていたもので、Xは、産休、勤務時間短縮を取得していたところ、回覧文書によって、これらが欠勤日数に算入され、90%条項により賞与が支給されなくなることを知らされたわけです。
したがって、本件90%条項は、その内容もさることながら、賞与の支給の可否という極めて重大な労働条件の周知を「回覧文書」という一般的には軽便と言えるような方法によって行ったという、その手段においても非常に問題があったといえます。会社としては、労働条件の変更については、その真意が間違いなく社員に伝わるように丁寧な説明をすること等も通じて、産前産後休業や短時間勤務制度等の制度を利用しやすい環境の整備が求められます。
著者:君嶋 護男(元労働大学校長)