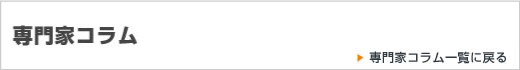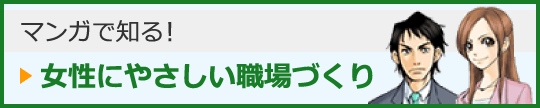- 母性健康管理とは
- 母健連絡カードについて
- 母性健康管理に関する用語辞典
-
母性健康管理に対する企業の義務
-
職場における母性健康管理の推進
-
働きながら安心して妊娠・出産を迎えるために
- 母性健康管理に関するQ&A
- 産前・産後休業、育児休業の自動計算
- 困った時の問合せ先
- 女性にやさしい職場づくり 相談窓口
- 申請書様式ダウンロード
- 母性健康管理に関するデータ・資料集
- 皆さまから寄せられたご相談に専門家がお答えします
- 専門家コラム
- マンガで知る!女性にやさしい職場づくり
- サイトマップ
- 働く女性の心とからだの応援サイト
働く女性の心とからだの応援サイト > 妊娠出産・母性健康管理サポート > 専門家コラム > COVID-19で変わる職場と母性への健康配慮

株式会社JUMOKU 代表取締役/産業医
長井 聡里
COVID-19で変わる
職場と母性への健康配慮
今、皆さんはどのような職場状況下で働いておられるでしょうか。2020年春は、ちょうど「働き方改革」が中小企業にも義務化される頃合いでしたが、奇しくも新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によって、働き方のみならず新しい生活様式として日常までもが変わりました。これにより在宅勤務を余儀なくされ、期せずして働き方を変えた企業も増えました。けれどこの問題は世界中の誰もが当事者であり、ひとまず日本では緊急事態宣言解除により徐々に経済活動や行動の自由化が再開されつつも、次なる感染拡大も懸念され、世界を見渡せばまだまだ先の見えない現状です。
このような非常事態下でも安心安全に産めるよう、全国の産科医療関係者が一丸となって叡智を結集し協力体制を築いてくれています。とはいえ、不妊治療も延期され、里帰り分娩やパートナーの立ち合い分娩も制限されるなど、女性達が思い描いていた「新しい命を授かる」喜びは、不安や孤独との闘いでしか得られない辛い状況にあります。
まさに自らが医療の最前線でCOVID-19と闘っている女性達、外出自粛要請がなされた中でも職場へ足を運び続けた女性達、在宅勤務となって休校中の子供達の世話をしながら働くことに悩む女性達、非正規労働でたちまち雇用不安にも直面した女性達、さまざまな立場で、産むことへの不安がより一層増しています。
幸いこのCOVID-19は一般に比べ妊婦はかかりやすいとか重症化しやすいといった報告はありません。とはいえ妊娠中はそもそも使用できる薬が限られたり、もう一つの命を育む身体への変化に戸惑い、どうやって新しい生活様式に馴染めばよいのか悩んだりします。もし感染した場合は、帝王切開の可能性や特別な産科管理下におかれ、赤ちゃんとの対面や授乳も制限され、産後もこれまでにない孤立した心理状態におかれる可能性が現状ではぬぐえません。
このような不安いっぱいで妊娠出産を迎える女性労働者の感染リスクを下げるため、職場ではどのような対策を取り支えることができるでしょうか。このコラムを読んでくださっている皆さんは、それらの情報が随時このサイトに集約され、制度や運用をすでに正しくご理解ご対応いただいていることでしょう。それでも産業医として感じたことをひとつだけ述べておきます。
通常、妊娠初期の段階では、「職場に迷惑かけたくない、公表した後に流産したら嫌だな」などから、本人も職場も安定期に入るまで妊娠の公表を控え、結果、必要な母性健康管理が行き届かない職場があります。けれど今回のような未知のウイルスに対して、健康配慮の必要な労働者を、早急に把握し守れるか検討に入ったとき、妊娠初期の段階から女性労働者をすべて把握できる体制になっていないことがわかったりします。母性健康管理措置は女性労働者の申請に基づくものではありますが、妊娠中の労働負荷や職場環境に関して初期に関わることで予防的に立ち回ることが可能です。いざという時、産科主治医とも連携できるよう、産業医等の産業保健スタッフや男女雇用機会均等推進者との連絡体制を構築し、一歩先をゆく健康管理、健康の危機管理、健康経営へとつないで欲しいところです。
(令和2年7月公開時点の情報です)
母性健康管理とは
ご相談窓口
ダウンロード
企業ご担当者の方
一般財団法人 女性労働協会
〒105-0014 東京都港区芝2-27-8 VORT芝公園8階厚生労働省委託 母性健康管理サイト
(C) Ministry of Health, Labour and Welfare, All Rights Reserved.