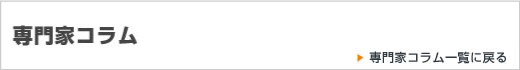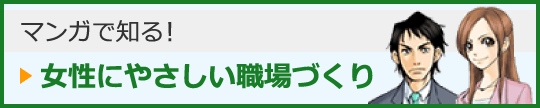さくら社会保険労務士事務所 社会保険労務士
脇本 美緒
向き合い方で決まる!労使共に
より良い育休復帰をするためのポイント
女性は子どもができたら退職が当たり前の時代から、仕事を辞めずなんとか育児をしながら働ける時代になりました。しかしながら実態は、様々な不安を抱えながら育休復帰をしている方が多いのではないでしょうか。
妊娠報告、職場復帰の希望を受けた管理職の方から、「今後、どのように向き合っていけばよいか教えて欲しい。」というご質問をいただくことが多くあります。そうなんです!この向き合い方がより良い育休、職場復帰につなげられる“つぼ”なのです。それでは、労使共に円滑に育休復帰を進めるための3つのポイントを紹介いたします。
「おめでとう」と妊娠を祝福した後、まず就業規則等に妊娠、出産、育児期についての制度が整備されているか、制度がある場合でも法改正前の古い規定になっていないか確認し、適正な規定を作成しましょう。そして社内全体、経営層、対象者へ周知を行います。対象者の周知はわかるけどそれ以外の人にもなぜ周知?と思われるかもしれません。これは、全体に説明することで育休取得に対する理解や協力が得られやすくなるためです。改まった研修でなくとも朝礼等でも行えますし、何といっても「育児休業が取れますよ!」という発信は、本人はもとより育休取得予備軍の社員にも心強い情報となりますので波及効果は大きいと言えます。また、前述の周知と重なる点もありますが、育児休業を取得しやすい環境づくりのためにも、育児休業や産後パパ育休に関する①研修、②相談体制の整備、③自社労働者の取得事例の収集・提供、④取得促進に関する自社方針の周知のいずれか1つ以上を実施することが法律で定められています。
次に、対象者と管理職、人事担当者が面談を行います。面談は少なくとも2回は行うことをお勧めします。体調面や業務の引継ぎ、今後の働き方、心配な点など、齟齬がないようコミュニケーションを図ります。この時などに、育児休業制度や産後パパ育休制度とその申出先の部署(総務課など)、休業中の社会保険料の取扱いや育児休業給付についても説明することが必要です。もし、面談ができない様な場合でも、これらについては、書面で交付するか、本人が希望する場合にはFAXや電子メール等で説明を行ってください。その上で、制度の利用希望に関する意向の確認まで行う必要があります。特に第一子妊娠の場合は、初めて聞くことばかりですので丁寧に行うことが肝心です。
育休期間では、復帰に向けてコミュニケーションを取るようにしましょう。会社からは定期的に社内の様子や会議議事録、人事等の情報提供を行います。育児にも慣れ復帰間近の場合、対象者が希望すれば業務についてのマニュアル等を渡してもいいかもしれません。また、この期間にスキル・アップを図りたいと思う方もいるかもしれません。会社が思う以上に本人は、仕事の空白期間に不安がありますので無理のない形で支援することも検討するとよいでしょう。2ヶ月ごとの育児休業給付金申請手続きのために(可能であれば赤ちゃんも一緒に)会社に来る時間を利用して意思疎通を図り、職場復帰へつなげていくことをお勧めします。
最後に復職についてお話します。この時期は、多くの復職者が復帰への不安や仕事と育児、家庭とのバランスで悩む場面に遭遇します。復帰する社員はこどもの突発対応など、自分の意志ではどうにもならないことに対して申し訳なく思っていますので、できる限りのことを頑張ろうとします。しかしこれだけはどうしようもありません。そのため上司は、就業環境を正しく把握し、優遇ではなく“適度な配慮”をすることが必要となってきます。例えば、「時間に制限がある中でベストを尽くすため、あなたは何ができるか?」「そのためには会社はどのような支援が必要か?」面談を通して確認します。そこを聴くことでおのずと対応する内容が出てきますし、新たな信頼関係が構築されることも間違いありません。
女性目線の経営が利益を伸ばすことは既知の事実となっています。妊娠、出産、育児期をマイナスイメージで考えるのではなく、個々のライフイベントで得られる経験が仕事の一助となり、ひいては会社の持続的な経営発展につながると考えてはいかがでしょうか。
関連情報
母性の健康を守るための法律や会社の役割についてご紹介します。
女性労働者が仕事と育児の両立を図れるよう、会社も一緒にサポートする環境をつくりましょう。