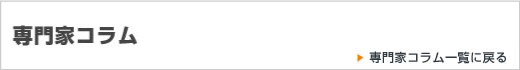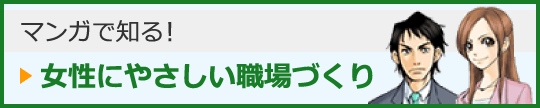産業医科大学 産業生態科学研究所 教授
産業医実務研修センター長
森 晃爾
妊娠を希望する女性または妊娠中の
女性の化学物質の取扱いの考え方
以前、女性を就かせてはいけない有害業務として、女性労働基準規則の規定を紹介しました。この女性労働基準規則が改正され、平成26年11月1日より施行されました。今回の改正は、発がん性を有する有機溶剤が有機溶剤中毒予防規則の措置対象物質から特定化学物質障害予防規則の措置対象物質に変更になっただけで、必要な対応が実質的に変わったわけではありません。しかし、女性労働基準規則で規制されている物質は、あくまでも法令で作業環境測定により化学物質の濃度を測定することが義務付けられている物質のみです。産業界には、稀な物質も含めればその何百倍もの化学物質が使用されています。そこで、この機会に、妊娠を希望する女性または妊娠中の女性の化学物質の取扱いに関して、基本的な考え方を整理しておきたいと思います。
様々な化学物質を販売・譲渡する場合には、安全データシート(Safety Data Sheet: SDS)を提供することが基本となっています。現在の法令では、640物質だけが義務となっていますが、国連の規定で危険性または有害性があるとされる約4万物質についても努力義務となっているため、ほとんどの化学物質について、購買者は何らかの有害性の情報を得ることができるはずです。ここでいう有害性の情報は国連によって標準化されており、以下の9つ有害性に分類されています。すなわち、急性毒性、皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷性/刺激性、呼吸器感作性または皮膚感作性、生殖細胞変異原性、発がん性、生殖毒性、特定標的臓器/全身毒性、吸引性呼吸器有害性です。それぞれの有害性の説明はここでは省きますが、このうち妊娠と関係する有害性は、生殖細胞変異原性と生殖毒性です。よく似た名前なので混乱しやすいですが、生殖細胞変異原性は奇形を引き起こす可能性、生殖毒性は不妊を引き起こす可能性とも言い換えることができます。安全データシートに、これらの性質が存在することが明記されている物質は、妊娠を希望する女性または妊娠中の女性が取扱う際には、注意が必要です。
それでは、まったく取り扱っていけないかというと、そうではありません。要は曝露の程度が小さければ問題ないということです。化学物質には、様々な科学的な知見をもとに出された許容濃度と呼ばれる、これまでなら妊娠中かどうかに関わらず、健康影響はほぼ生じない濃度が設定されています。例えば、ドラフトの中での作業など、十分な管理がされている職場であれば、基本的に問題ないことになります。
このような原則を理解しておけば、法令の規制がない化学物質であっても、妊娠中に化学物質を扱う業務を続けてもいいかについて、ある程度判断することができます。しかし、いくら知識を得て、頭で理解しても、“やはり不安である”という方は、職場の産業医や衛生管理者に相談することをお勧めします。
関連情報
労働基準法における母性保護規定に示されている妊産婦を就かせてはならない具体的業務をご紹介します。
化学物質を取り扱う事業主の皆さまへ 女性労働基準規則の一部が改正されます(厚生労働省リーフレット)
女性労働基準規則の改正について詳細をご紹介します。