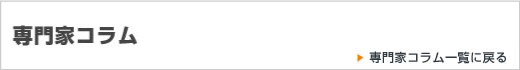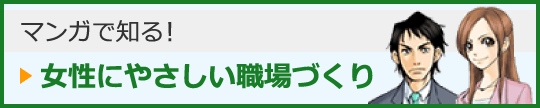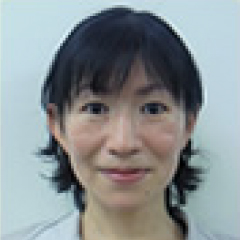
JR東日本健康推進センター
吉田 純子
健康管理部門との関わり方
1999年に男女雇用機会均等法が改正され、女性でも深夜帯や休日に勤務することが可能となり、女性が活躍できる場所が広がりました。それから10年余を経て、現在では女性が学校を卒業し、就職しても以前のように結婚や妊娠などで退社するケースは少なくなりつつあります。そして妊娠中や出産後も仕事をし続けることが当たり前になってきました。妊娠は病気でないといっても、身体や体調の変化もあり、非妊娠時と同じ働き方をすることは難しいと思います。妊娠中の業務への配慮、産前産後休暇、育児休職の制度取得などに不慣れな部分がまだまだ労使双方にあるかもしれません。妊婦健診で重度のつわりや切迫流早産、妊娠高血圧症などの異常が指摘されて、現在の仕事にそのまま就き続けることが難しい場合、主治医からの指導事項がそのまま職場に伝わればいいのですが、難しい場合は母性健康管理指導事項連絡カードを利用したり、健康管理部門(産業医、保健師などの産業保健スタッフ)に相談するのもいいかもしれません。
軽易業務への転換や、深夜業や残業、休日出勤の免除などは申し出れば受けられることになっています。しかし実際申し出をするとなると、ためらいを感じてしまう方もいらっしゃるかもしれません。50人以上の職場では産業医が選任されているはずですし、1000人以上の職場(有害業務がある一部職場では500人以上)では専属産業医が選任されているはずですので、是非御相談してみてください。相談したことがない、どう相談したらいいかわからない、という方は職場の衛生管理者の方などに聞いてみてください。産業医は医師であり、職場の業務内容についても知りうる立場にあります。労働者の健康を管理するという職務のもとに選任されているわけですから、妊娠中の労働者が健康に就業するために作業内容の配慮について助言できる立場にあります。職場によっては産業医や保健師による健康相談日を設けているところもあるでしょう。働く上で、体調を考慮した産業医からの助言があれば職場も受け入れやすいかもしれません。是非健康管理部門を上手く活用していただき、無理のない働き方をして健やかな出産の後、元気に職場復帰していただきたいと思います。
関連情報
妊娠中のつらい諸症状を少しでも緩和し、安心して働くことができるために知っておきたい法律や制度をご紹介します。
「母性健康管理指導事項連絡カード」は、医師等の女性労働者への指示事項が適切に事業主に伝達されるためのツールです。
妊娠中の症状や職場での対応、母性健康管理の取り組み、法律など、迷ったとき・困ったときの問合せ先です。