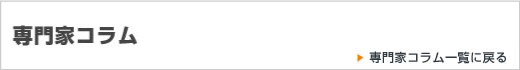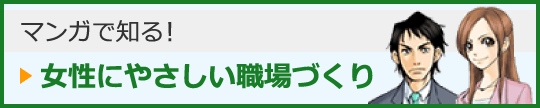産業医科大学 産業生態科学研究所 教授
産業医実務研修センター長
森 晃爾
女性を就かせてはいけない有害業務
−女性基準規則の改正

平成9年の男女雇用機会均等法の改正の際、それまで女性が就くことができなかった多くの業務が解禁になりましたが、いくつかの業務については母性保護の観点から制限が残りました。その一つが、「鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、シアン化水素、アニリン、その他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」でした。
しかし、「なぜ、これらの業務に女性を就けていけないのか?」、「それ以外に制限しなければならない化学物質はないのか?」、「どの程度の濃度なら大丈夫なのか?」といった疑問に対して、科学的根拠が不足しているか、根拠があっても利用できる形で整備されていなかったため明確に答えることができませんでした。そのため、規制が実情に合わないことは明らかでしたが、改正が見送られてきた経緯があります。
昨今、化学物質の危険有害性等の情報については、国連主導でGHSと呼ばれる世界統一基準ができ、わが国でもそれに合わせた各種の改正が行われてきました。その整備が整ったことを受け、この度女性労働基準規則の一部が改正され、規制の対象物質や対象作業が変更になりました。(平成24年10月施行)
1.対象物質について
GHSに基づく有害性分類のうち、生殖毒性(性機能及び生殖能又は発生に対する悪影響)若しくは生殖細胞変異原性(生殖細胞に経世代突然変異を誘発)が存在すると知られているまたはみなされる化学物質(1Aまたは1Bに相当)又は授乳影響ありとされた物質で、法令で作業環境測定が求められている物質(25物質)
2.対象作業について
法令で送気マスク等の呼吸用保護具の着用が義務付けられている作業および作業環境測定の結果が第3管理区分である屋内作業場での業務。なお、今回の規制では、国内法で作業環境測定が求められている物質のみが対象となりましたが、規制の趣旨を勘案すると、GHS分類による危険有害性で同様の有害性が認められている未規制物質を取扱う作業においても、許容濃度を超える曝露の可能性がある作業については、女性の就労を控えることが望ましいと考えられます。
規制の変更内容
-
これまでの規制
対象物質 規制濃度 鉛 0.5mg/m³ 水銀 0.1mg/m³ クロム 0.5mg/m³ 硫素 1mg/m³ 黄りん 2mg/m³ 弗素 3ppm 塩素 1ppm シアン化水素 20ppm アニリン 7ppm -
新しい規制
対象物質 規制濃度 アクリルアミド 0.1mg/m³ エチレンイミン 0.5ppm エチレンオキシド 0.5mg/m³ エチレングリコールモノ
エチルエーテル5ppm エチレングリコールモノ
エチルエーテルアセテート5ppm エチレングリコールモノ
メチルエーテル5ppm 塩化ニッケル(Ⅱ) 0.1mg/m³ 塩素化ビフェニル 0.01mg/m³ カドミウム化合物 0.05mg/m³ キシレン 50ppm クロム酸塩 0.05mg/m³ 五酸化バナジウム 0.03mg/m³ N.N-ジメチルホルムアミド 10ppm 水銀及びその無機化合物 0.025mg/m³ スチレン 20ppm テトラクロルエチレン 50ppm 50ppmトリクロルエチレン 10ppm トルエン 20ppm 鉛及びその化合物 0.05mg/m³ 二硫化炭素 1ppm 砒素化合物 0.003mg/m³ ベータプロピオラクトン 0.5ppm ベンタクロルフェノール及び
そのナトリウム0.5mg/m³ マンガン 0.2mg/m³ メタノール 200ppm - 注)カドミウム、クロム、バナジウム、ニッケル、砒素の金属単体、マンガン化合物は対象とならない。
関連情報
労働基準法における母性保護規定に示されている妊産婦を就かせてはならない具体的業務をご紹介します。
母性保護のための「女性労働基準規則」の改正(厚生労働省HP)
「女性労働基準規則(女性則)の一部を改正する省令」の詳細をご紹介します。