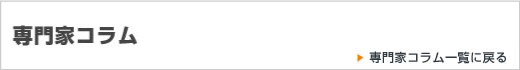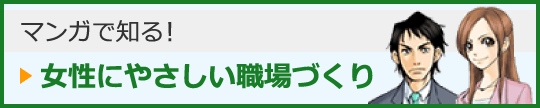特定社会保険労務士
海老根 葉子
働きながら妊娠・出産を迎えるために
やるべきこと

女性労働者の皆様こんにちは。
出産という大きな喜びと不安の中、お仕事を続けられることは精神的・肉体的にも大変なことと思います。
女性労働者(正社員、契約社員、派遣社員、パートタイムすべて平等に対象)の母性保護は、「労働基準法」、「男女雇用機会均等法」、「育児・介護休業法」などの法律において整備されています。
関連する主な項目を簡単にまとめてみます。
- 1.産前休暇(女性が請求した場合に出産予定日の6週間前から取得)と産後休暇(出産の翌日から8週間・・6週間までは請求の有無に関係無く与えなければならない)。
- 2.請求があった場合は、時間外・休日労働・深夜労働を命ずることはできない。
- 3.生後1年に満たない子を育てる女性は1日に2回各々30分の育児時間を請求できる。
- 4.妊娠等を理由とする不利益な取扱い(解雇等)を禁止する。
- 5.母性健康管理面から保健指導などを受けるための時間、また、通勤時の時差通勤などを確保するよう、事業主に命じている。
- 6.育児休業対象者は、原則、1歳未満の子を養育する労働者(男女共)。1人の子につき2回の取得(例外あり)。
- 7.小学校3年生修了前の子を養育する労働者(男女共)は子の看護等休暇(1年に5日まで)を請求することができる。
※現行では、1年に5日まで、子が2人以上の場合は10日
しかし、どんなに法律が整備されていても、会社という枠の中で適正に理解そして運用されなければ、意味を持たなくなってしまいます。残念ながら、それを象徴するようなトラブルや相談は絶えることがありません。働く女性の心構えとして自分の会社で上記の内容に関する措置について記載があるのか、あるいはきちんと講じられているのか、確認することが必要です。
また、勤務時間の短縮や休業・休暇に対する不就労分の給与の取扱について明記されていなければ是非確認して下さい。近年出産件数の減少に伴って社内での前例も減少し、企業側も労働者の請求によって初めて考えようとするケースが少なくありません。一方、企業によっては妊産婦等女性労働者がいかに不安なく勤務を継続できるか考え、十二分に対応しているところもございます。こういう環境の中で子供を産み・育てていけるなら、結局、労働者の労働力が企業に大いに反映され、今後の発展につながるのではないでしょうか。
私たちはメールにてご相談を承っておりますので、もし何か悩まれた場合はご一報下さい。法律と照らし合わせて、どれが問題点なのか、どうすれば解決できるか一緒に考えます。上記の法律の他に、健康保険法(出産手当金)、雇用保険法(育児休業給付)、厚生年金保険法(育児休業終了の際の給与の改定等)に係る件についてもご相談下さい。私たちの思いは、皆様が整った環境の中お仕事を継続され、元気な赤ちゃんを産み・育てることですから。
関連情報
無事に出産を迎え、体力回復の後、職場復帰を果たせるように、出産が迫った時期と産後しばらくの期間は、休業を与えてあげましょう。
女性労働者が仕事と育児の両立を図れるよう、会社も一緒にサポートする環境をつくりましょう。
出産前・出産後、働く女性が取得できる休業など、ワーキングママを支える法律をご紹介します。
幼児を養育しながら働くのはとても大変。育児中の働くママを応援する法律をご紹介します。