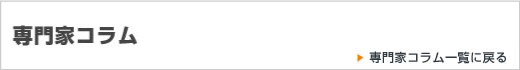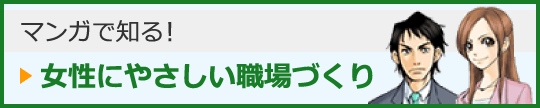(財)放射線影響研究所理事長
大久保 利晃
母性保護と性差医学

本稿の主題は、広義の母性保護を生物学的な性差の問題(SEX)と文化社会的な性差(GENDER)に分けて考えることである。
女性労働の問題はその両者を同時に含むことが多く、それらを分けて議論を進めないと混乱を生ずることがある。労働者の母性保護で説明すると、妊娠・出産は女性にしか起こらない特別な事象である。しかし育児は男女両性の義務であり、それが一方的に女性のものとされてきたのは、歴史的・文化的な背景によるものである。
また、妊娠の進行に伴う就業上の措置や産休などは、性差に由来するものである。しかし、大企業の産前産後の支援策に関する調査で、「開業以来女子社員が妊娠した場合はすべて円満退社しているので、産前休暇を取得した例はありません」というベテラン看護職からの自慢げな回答に驚かされたことがある。これはほんの一例で、この他にも妊娠出産に関しては、長い間に女性に不利な「特別扱い」の社会的差別が数多くでき上がっている。
このような社会的差別を排除するため、通称男女雇用機会均等法が20余年前にできて以来、女子労働者の立場は少しずつ改善が進んだ。その結果、女性労働者を「保護」の対象と位置づけてきた労働基準法(以下労基法)の考え方が、皮肉なことに、むしろ女性の雇用機会と社会進出の障碍となり、逆差別になりつつあるという認識が生まれ、約10年ほど前に、深夜労働禁止などの女性保護規定を原則として全廃する労基法の大改正が行われた。
改正作業の途上では、「深夜勤務は本当に女性の負担にならないのか?」という難問が、行政当局をはじめ経営、労働双方から次々と発せられ、我々専門家は大いに当惑したものである。そのような時期を経て、深夜勤務を解禁するコンセンサスができ上がった。社会的保護を緩める代わりに、性差である妊娠出産期に対してはより手厚い保護施策を導入すべきだという考え方から、同時にその時母性保護施策の強化が実施されたのである。
性差医学という側面から見ると、改めてびっくりすることも少なくない。レストランにお子様ランチはあっても成人男女の区別は無く、大抵は男女同じ量が盛られた皿を持ってくる。当然女性は食べ残す結果にならざるを得ない。もしそうでない人がいれば、その結末は一目瞭然ということになる。薬用量も、大部分は大人と子供の区分だけしかない。
健康診断の判定基準も従来から男女別の区別はほとんど無かった。しかし、健診で使う大部分の検査で基準値に有意の性差があり、例えば総コレステロール値の場合、中年までは男性の方が高いのに対し、高齢になると女性のほうが高くなるという、明らかな性差が存在している。
この差は、病気の診断や治療方針の決定を左右するほどではなく、臨床医学にとっては無視できる範囲である。しかし、保健指導で性差を無視すると指導精度を下げかねない。健康者に対する医学が、病者のそれと同じとは限らないことを認識すべきである。
関連情報
女性労働者が身体への負担を与えることのないよう配慮し、十分に能力を発揮することができる環境を整えてあげましょう。
無事に出産を迎え、体力回復の後、職場復帰を果たせるように、出産が迫った時期と産後しばらくの期間は、休業を与えてあげましょう。