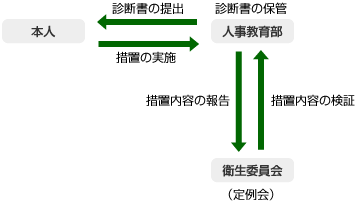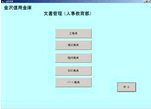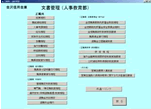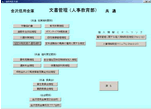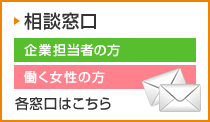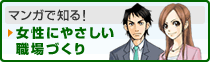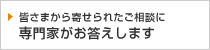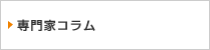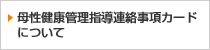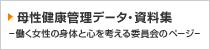事例インタビュー:金沢信用金庫(石川県金沢市) 人事教育部 池端進 様
──健康管理および母性健康管理に関する企業のポリシーを教えてください。
| ・ |
健康管理は役職員本人の義務であり、企業はこれをできる限りサポートします。 |
| ・ |
母性健康管理を含め、職員が能力を120%発揮できるサポートをしていく。お客様と企業と従業員が「いっしょにGOODLIFE」できることを企業のポリシーとしています。 |
| ・ |
従業員は長く働き続けてくれることを前提に会社組織自体が教育や研修にコスト・時間をかけています。 |
|
 |
 |
──あなたの企業の健康管理体制と、診断書の提出から、措置、保管までの流れを教えてください。
保健管理スタッフは、嘱託産業医1名、衛生管理者3名(人事教育部内6名)です。
診断書の提出から保管の流れは、本人から人事教育部に提出され保管されます。措置については人事教育部が本人に(必要であれば部店長にも)状況を詳しく聞いたうえで、医師の指導内容があればこれを尊重し実施します。実施内容は衛生委員会の定例会において報告され、検証されています。
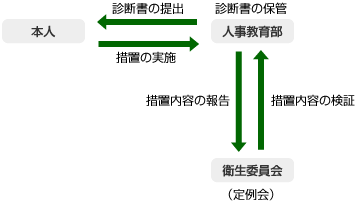
──あなたの企業の「母性健康管理」に取り組むための実施体制を教えてください。
母性健康管理を担当するのは人事教育部です。機会均等推進責任者も人事教育部に所属しています。
制度の改正運営は厚生労働省の指針や職員のニーズを把握しながら人事教育部、衛生管理者を含む衛生委員会で試案を作成し、労働組合の意見を聞き、役員の承認を受け施行しています。
また、人事教育部では、母性管理に関する制度について現場管理者の認識が不十分で不適切な扱いがあった場合は改善命令を出すという強い姿勢で臨むことを表明したが、制度自体周知徹底されており実際の改善命令は出された実績はありません。
部店長と半年に一度定期的に面接する面接シートの内容を改定し、就業環境や、家庭状況、個人の健康状態等々について相談できる態勢を整えました。導入後はコミュニケーションが良くなり、母性保護面を含め現場管理者の配慮も充実しています。
また、これに伴い産婦人科検診等のための休暇等による人員の不足も、相互協力や他店よりの応援などがスムーズに行われています。
──母性健康管理の制度について、具体的な取り組み内容を教えてください。
健康診査等を受けるための時間の確保
法定通りの回数で、勤務時間内の通院を有給で認めています。病院等の混雑により予定時間を大きく上回る場合は部店に連絡をさせています。特に通院時間の上限は設定していません。
産前・産後休暇、通勤緩和
産前産後休暇は法定通りの基準で無給。医師の指導による通勤緩和は、1日30分以内で遅出、繰上げ退出による勤務時間の短縮を認め、有給として扱います。
但し、母性の健康状況により30分または1時間の時差勤務とする場合もあります。
また、つわり休暇は妊娠12週まで通算7回まで請求でき無給です。
休憩時間
医師の指導による休憩時間の延長は原則1時間以内で必要とされる時間とするが、本人の状況により相談のうえ、場合によってさらに30分延長を認めています。これらの休憩時間の増加分は勤務延長を求めないし、賃金の減額はしません。
諸症状に対する措置
<作業の制限>
諸症状に対応する措置として、医師の指導事項に基づき業務の制限に対処しています。
<勤務時間の短縮>
勤務時間の短縮として1ヶ月以上の期間、短時間勤務制度の適用をうける場合は短縮時間相当分を無給としています。休業は無給であるが、実際は年次有給休暇の消化によって対応されています。
その他
このほか、当金庫では人間ドック受診希望者に、全て補助を実施しており、特に女性職員には婦人科検診を推奨しており、近年増加している乳がん、子宮がんなどの予防早期発見の態勢をとっています。また、健康保険の被扶養者である配偶者の人間ドック受診も補助しており、家族ぐるみの健康管理に取り組んでいます。
──母性健康管理制度について、社内でどのような周知・教育活動を行っていますか。
管理者への周知・教育活動
管理職に対しては新任次長時と年2回の人事担当者会議(各部店の人事担当者が出席)で規程や厚生労働省の資料を基に周知させています。
女性労働者への周知・教育活動
妊娠中の女性労働者への制度周知はイントラネットでの規程の閲覧や同僚の経験談、医師によるアドバイスなど必要レベルは満たしています。個別的な相談は人事教育部員である女性の産業カウンセラー資格者が対応しており、相談者の同意を得て人事部門へ相談し個別対応をしています。
育児休業中の女性労働者に呼びかけ任意参加で土曜日に制度利用や子育てに関する情報交換会を実施しました。 |
 |
|
──妊娠中・産後の女性労働者に対して、どのような配慮をしていますか?
妊娠の申し出
随時、自発的な業務上の報告事項となっている。報告時期迷っている場合でも半年に一度の部店長との面接では必ず報告されています。以前から妊娠したら育児休業を取得し、仕事を続けるという環境になっています。報告後、管理者は母性保護に留意しています。
相談窓口
相談窓口は、人事教育部員である女性の産業カウンセラー資格者、社会保険事務担当(女性)、人事労務担当がそれぞれの分野で相談に当たっています。制度の確認や、産後休暇以降の給付金等請求手続きの説明は活発に行われています。
医学的なことは主治医に、心理的なことは企業内の産業カウンセラーもしくは契約し営業店を巡回している外部産業カウンセラーが担当しています。
主治医等からの指導事項があった時の配慮
主治医に就業環境に関することを指示されたら、女性労働者及び管理者は軽微なものでも人事教育部へ報告する態勢になっています。
休憩室、分煙等職場環境の整備
本支店に横になれる場所のある休養室があります。また店舗によっては全面禁煙となっているが、多数は分煙に留まっています。
──母性健康管理指導事項連絡カードをどのように利用していますか?
母健連絡カードの入手方法
イントラネットからダウンロードできるようになっています。制度利用のため提出されるのは『母健連絡カード』より『診断書』のほうが多いです。
提出、措置、保管の流れ
提出から保管の流れは、本人から部店長、人事教育部に届けられ保管されます。
措置については、部店長において対応できるものはそこで対応し、人事教育部へ内容が報告されます。
事教育部で措置を決定する場合は、決定後本人と部店長へ通知し、制度利用状況として衛生委員会へ報告される態勢になっています。
プライバシーへの配慮
プライバシーの配慮は、雇用管理における個人情報の取扱い規程や、衛生管理者や衛生委員としての守秘義務により守られています。措置について所属部店内のメンバーの理解と協力が必要な場合は、本人の了解を得て必要部分のみを説明しています。
──母性健康管理の取組において、健康管理部門や主治医とはどのような連携を図っていますか?
衛生委員会(衛生管理者、人事教育部で構成)では、制度利用状況報告により措置の適切性を再確認する。必要であれば本人の意見や主治医の意見を求めることもできます。
──妊産婦が就業制限業務に従事している場合、どういった対処をしていますか?
該当業務はありません。
──産休及び育休後の職場復帰のために、どのような取組を行っていますか?
上司・人事等相談システム
産休の2週間程度前に復帰日を人事教育部が確認し、復帰3ヶ月程度前に本人に育児環境等(本人や子の健康状態含む)を報告してもらい、内容を確認し配属先の変更など必要な措置があれば検討し、1ヶ月前に本人と面談し通知、決定します。
決定後は本人の了解を得て部店長に配慮すべき事項を伝え、本人が部店へ事前訪問のうえ、上司と復帰後の担当職務について打ち合わせを行います。
休業中の代替要員の確保
補充は原則派遣職員により対応しているが該当店舗の人員構成によっては直近の人事異動等で対応が必要なケースもあり、部店長と相談のうえ人事管理担当主導で採用の担当と調整し対応しています。
──育児休業制度について教えてください。
制度内容で法定を上回るのは、期間で法定より1日長く子の1歳の誕生日までと、保育園等の事情による延長は1歳前から可能にしている点。無論非正規職員もすべて同条件で利用対象となっています。
平成18年までの状況は直近3年間で44名(うち男性正規職員1名、女性非正規職員4名)が取得。取得率100%、復職率96%であり、平成19年9月末の状況は15名が取得中(うち非正規職員1名)です。
──母性健康管理システムが効果的に機能した事例あるいは問題となった事例はありますか?
勤務時間内の通院を有給で認めているため繁忙日を避けた利用がなされており、職員が企業や同僚に対して無理をしない範囲で配慮して制度利用をしてくれます。企業に対するロイヤリティーが高まったと考えています。