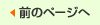 |
5/5 |
|
【母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)】
母健連絡カードとは、時差通勤をはじめ作業の軽減、休憩、勤務時間の短縮、休業など、医師等が必要であると認めた指導事項を的確に会社に伝えるために利用するツールです。これを提出することにより、記入事項に従った措置を受けることができます。
【時差通勤】
医師等から通勤緩和の指導を受けたことが妊産婦から申出があった場合には、ラッシュアワーの混雑を避けて通勤することができるように通勤緩和の措置を講じなければなりません。
(男女雇用機会均等法 第13条)
【産休(産前休業・産後休業)】
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)(いずれも女性が請求した場合に限る)、ただし、出産後6週間を経過した女性労働者本人が請求した場合に、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えありません。
(労働基準法第65条第1項、第2項)
【妊産婦の時間外労働の制限】
妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせることはできません。
(労働基準法第66条第2項、第3項)
【育休(育児休業)】
労働者が申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます。一定の場合、子が1歳6か月又は2歳に達するまでの間、育児休業をすることができます。
(育児・介護休業法第2条、5条〜第9条)
また、育児休業を申し出たことや取得したことを理由とする解雇その他不利益取扱いは禁止されています。
(育児・介護休業法第10条等)
ご相談がある場合は、各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)までお問い合わせください。
山下さんの会社も、人事部の松井さんの頑張りと、阿部課長や山下さん自身の制度に対する理解によって、職場の雰囲気も良くなり、制度を利用しやすくなったようですね。
上司は、女性社員から妊娠の申し出を受けたら、まず最初にお祝いの言葉をかけてあげて、本人の不安を和らげてあげましょう。その後、母性健康管理制度や育児休業制度などについて説明しましょう。妊娠・出産・子育て期の女性を支える社内制度について分かりやすくまとめたパンフレットなどを作成しておくことも効果的です。
出産を控えた女性社員は、自分の身体のことのみならず、仕事や職場の人間関係など、今後どのように対応すべきかを1人で悩んでしまうことも少なくありません。本人の体調や不安なことなどについて話をよく聞き、産休・育休の取得予定や現在の仕事の状況や引き継ぎのスケジュール、復帰後の希望などを話し合っていくことが大切です。日頃からの会話を欠かさずに、本人が率直に要望や不安を話せる雰囲気づくりに心がけましょう。
(※特に、育児休業制度等の個別の周知とその取得意向の確認については、育児・介護休業法で実施が義務づけられています。)
また、職場の社員が妊娠・出産を迎える女性社員に対して配慮できるよう、上司が率先して他の社員とコミュニケーションを図るようにしましょう。定期的に実施されている会議や打ち合わせなどの場面で、職場の社員に対して、制度の趣旨や内容について説明するなど、女性労働者が円滑に制度を利用できる環境づくりに努めましょう。
女性労働者が産前・産後休業後、引き続き育児休業を取得することを希望している場合、休業期間が長期間にわたる場合もあります。管理職は、休業中の代替要員を確保したり、業務分担を見直して部署内で調整するなど、職場の状況に応じて適切な雇用管理を行う必要があります。
彼女の仕事を周囲が負担するようなことになる場合は、具体的な業務配分や人員配置などについてきちんと調整・説明した上で、彼女を職場全体でサポートすることの重要性を伝えるようにしましょう。
|
|
|
妊娠を報告する時期は、妊娠してすぐという人、体調が安定してからという人と考え方は様々だと思います。しかし早めの報告があれば、職場で早い時期から身体の負担に配慮した環境づくりをすることができますから、無理をして体調を崩すような危険を回避することができます。妊娠がわかったら、上司にすぐに報告することが大切です。
産前・産後休業、育児休業までの仕事の引き継ぎについては、上司との話し合いを進めながらしっかりと行ないましょう。特に、育児休業を取得する場合は、休業期間が長期間にわたる場合もあることから、所定の申出手続をあらかじめ確認しておき、期限までに希望する育児休業期間を明らかにして申出を行いましょう。また、これから出産を迎えるまでに、体調の変化などで急に休まなければならないような事態も起こります。日頃から上司や同僚と担当する業務の進捗について情報共有するなど、コミュニケーションを欠かさないようにしましょう。
上司をはじめとした周囲の多くの人々があなたを支えてくれることになります。感謝の気持ちを忘れずに、その気持ちをいつも伝えるようにしましょう。
|
 |
 |
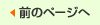 |
4/5 |
|
第5話 「さよなら会」より「おかえり会」がいいよね
|